| ■ニュース・バックナンバー:2009 |
| ニュース・2009 | セミナー |
| ■2016年│■2015年│■2014年│■2013年│■2012年│■2011年 ■2010年│■2009年│■2008年│■2007年│■2003年・2004年 |
| ■2009年12月8日 10月28日開催 第3回中山セミナーのご報告 | |
 |
去る10月28日、シアトル在住の米国歯周病専門医、中山吉成先生をお迎えして、歯周病セミナーを実施しました。 今回で3回目になりました。歯周病の治療にとって鍵となるのは、まず、皆さんの日常のプラークコントロールです。歯を磨いているだけでは、歯と歯肉の境目や歯の間のプラークは取れませんから、フロスや歯間ブラシなどの適切な清掃指導を受けて、それを身につけることが重要です。 >>くわしく:第3回 中山セミナー(ニュースアーカイブ) |
■このページのトップへ戻る■
| ■2009年9月15日 当医院の治療、メインテナンスは来院患者さんの利益になっているか? (患者データに見る当医院の評価) | |||
| 医療は所詮サービスだと極論されることもありますが、物の売り買いのようなサービスとは明らかに違います。それは、ご自分の健康、とくにお口の健康を維持するという目標があるからです。一瞬の心地よいサービスが大切なのではなく、長期的に関わったときに、ご自分の歯がいかにいい状態で残せるのか、虫歯や歯周病を予防できるのか、その実力がどれくらいあるのかが問われていると思っております。 そのような意識のもと、この医院では、開設以来、患者さんに附随する様々な臨床データを記録、保存。蓄えられたデータを分析することで、当医院をご利用の皆さんが、当医院を利用しない場合に比べて、どれくらい利益を得ていらっしゃるか検討しました。 このようなデータは、長期的な地道な作業の蓄積がなければ、到底なし得ません。多くの医院では、恐らく、このようなデータを出したくても出すことはできないと思います。このような長期的評価のデータが出せることこそ、この医院の最大の強みです。 患者対応がいいというのは、当たり前のことです。そういう尺度だけで医院を選ぶことは必要ではあっても十分とは言えません。ネットの評判情報も、対応やコストなど、目先の目に見えることで判断されていることが大半です。しかも、そこには情報操作もあります。この医院では、少しでも皆さんが医院を選択する際に安心して、選択できる情報を提供することを目的にこのような情報を公開します。 | |||
| |||
 | |||
|---|---|---|---|
| (1)虫歯リスク検査(唾液検査)の結果を集計したものです。これを見ると、来院者の60%近くの方が虫歯菌をハイリスクに保菌していることがわかります。食生活やフッ化物の使用などもまだまだ十分に理解されているとは言えない状況であることが見て取れます。こういった、リスク検査を通じて、ご自分に合った予防プログラムを立案しています。 | |||
1)ミュータンス菌の数 虫歯の主な原因菌であるミュータンス菌の唾液中の数を計測しました。 一般的にリスク2以上は、虫歯菌危険度がハイリスクと言われています。 ・リスク0=1万以下/唾液1ml ・リスク1=1~10万/唾液1ml ・リスク2=10~100万/唾液1ml ・リスク3=100万/唾液1ml 2)乳酸菌の数 虫歯菌は、酸性の環境でより活発になります。ヨーグルトや漬け物などの乳酸菌、ラクトバチラス菌がお口の中に 多いということは、お口の中が酸性の環境になっている証拠です。虫歯菌にとって住みやすい環境になっていると言えます。乳酸菌は、虫歯の穴が空いたまま放置していたり、被せ物の縁に段差があって、食べ物のカスが停滞するような環境でよく繁殖します。 また食生活が、炭水化物や糖分に偏っていると、繁殖しやすくなります。食事習慣の改善と治療をきちんとすることが大切なのです。 一般的にリスク2以上は、虫歯菌危険度がハイリスクと言われています。 ・リスク0=1000/ml ・リスク1=1万/ml ・リスク2=10万/ml ・リスク3=100万/ml 3)唾液の中和能力 虫歯の原因菌は酸を出してはの表面を溶かします。唾液にはもともと酸を中和する能力があり、これを中和能力または緩衝能と呼ばれます。中和能力には個人差があります。黄色い試験紙に唾液を垂らして、5分後に変化を見ます。青くなれば完全に中和されています。緑、黄色がハイリスク。 ・リスク0=すぐに青色に変化 ・リスク1=ゆっくり青色に変化 ・リスク2=緑に変化 ・リスク3=黄色のまま 4)5分間の唾液量 唾液にはお口の中を洗い流し清潔に保つ効果もあります。唾液の量も個人差があり、唾液が少ないと虫歯のリスクが高まります。5分間、パラフィンガムを咬んで、はき出した唾液量を計量します。3.5ml以下がハイリスクです。 ・リスク0=10ml以上 ・リスク1=6ml以上10ml以下 ・リスク2=3.5ml以上6ml以下 ・リスク3=3.5ml以下 5)飲食回数 一度、口にものを入れると、ミュータンス菌はその糖分からエネルギーを摂取し酸を捨てます。その酸によって、歯の表面からカルシウムやリン などのミネラルが溶け出し(脱灰:ダッカイ、といいます)ます。しかし、40分くらい すると、唾液の中和能力により酸性度が薄まると、ミネラルは再び歯の表面に戻ります (再石灰化)。 一回の食事の度に、このような化学変化が起こります。食事の回数が多いと脱灰する時間が多く、再石灰化する時間が少 なくなり、その状態が長引くと、歯の表面に穴が空きます(虫歯)。 飲食回数は、できるだけ少ない方が虫歯にかかりにくいのです。 ・リスク0=3回以下 ・リスク1=4回(間食1回) ・リスク2=5回(間食2回) ・リスク3=6回以上 6)プラーク量 全ての歯の表面に対するプラーク(歯垢)の付着部位を%で表示します。 ・クラス0=5%未満 ・クラス1=15%以上 ・クラス2=30%以上 ・クラス3=50%以上 7)フッ素(フッ化物)の使用 フッ素の役割は、酸性環境で歯からミネラルが溶け出すのを阻止します。また、再石灰化のときに歯の表面にフッ素も入り、歯質を強化して歯を溶けにく くします。 ・リスク0=診療室で定期的+家庭で毎日 ・リスク1=家庭でのみ毎日使用 ・リスク2=来院時のみ使用 ・リスク3=使用してない
| |||
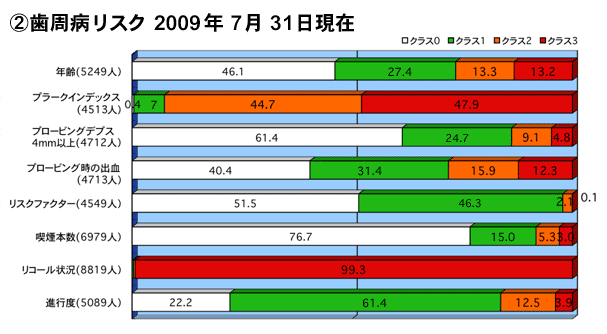 | |||
| (2)歯周病リスクの結果を集計したものです。深い歯周ポケットを有する方は、全体の15%、歯肉からの出血があるのは30%の方に見られます。喫煙経験のある方は、25%です。タバコは、歯周病のリスクとして、かなり大きな位置を占めます。この医院に来院するようになって、禁煙された方もかなりいらっしゃいます。殆どの方が、定期的に歯科医院を利用することがなかったことは、今の日本の現状を物語っています。治療をすれば請求できる医療保険制度のもと、何にもないときに自分の健康のために来院するという習慣が定着しなかったと思われます。当院のような存在が、そう言った意識に変化を与える契機となれればいいと考えています。 | |||
|
1)年齢 年齢とともに歯周病の進行しますので、高齢になるほどリスクが高くなります。 リスクの変化につきましては(3)歯周病進行度をご参照ください。 ・クラス0=30 歳未満 ・クラス1=30~40歳 ・クラス2=40~50歳 ・クラス3=50歳以上 2)プラークインデックス 全ての歯の表面に対するプラーク(歯垢)の付着部位を%で表示します。 ・クラス0=5%未満 ・クラス1=15%以上 ・クラス2=30%以上 ・クラス3=50%以上 3)プロービングデプス 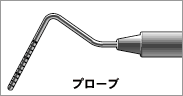 プローブと呼ばれる目盛りの付いた器具で、歯と歯ぐきの境にあるポケットと呼ばれる溝の深さを一歯につき最低4箇所計ります。深さ4ミリ以上あれば歯周病が疑われます。深さ4ミリ以上の%。 プローブと呼ばれる目盛りの付いた器具で、歯と歯ぐきの境にあるポケットと呼ばれる溝の深さを一歯につき最低4箇所計ります。深さ4ミリ以上あれば歯周病が疑われます。深さ4ミリ以上の%。・クラス0=10%未満 ・クラス1=10%以上 ・クラス2=30%以上 ・クラス3=50%以上 3)プロービング時の出血 プロービング時に出血した割合です。 ・クラス0=10%未満 ・クラス1=10%以上 ・クラス2=30%以上 ・クラス3=50%以上 4)リスクファクター 危険因子とは、歯周病になりやすい要因のことで、全身的と局所的なものに分けられます。リスク因子が多ければ歯周病になりやすいと言えます。 全身的リスク因子:糖尿病 女性ホルモン異常(更年期) リウマチ 膠原病 高脂血症 心疾患 肝臓疾患 血液疾患(白血病など) ダウン症候群 シェーグレン症候群 ベーチェット病 免疫不全 局所的リスク因:歯牙の形態異常 歯牙の近接 歯列不正 異常咬合・習癖 歯牙の挺出 病的移動 側方運動時の干渉 不適合治療 歯根破折 耳鼻科疾患既往あり 口呼吸 歯科医による不良治療 その他 危険因子の数・クラス0=なし ・クラス1=1つ ・クラス2=2つ ・クラス3=3つ以上 5)喫煙本数 6)リコール状況
| |||
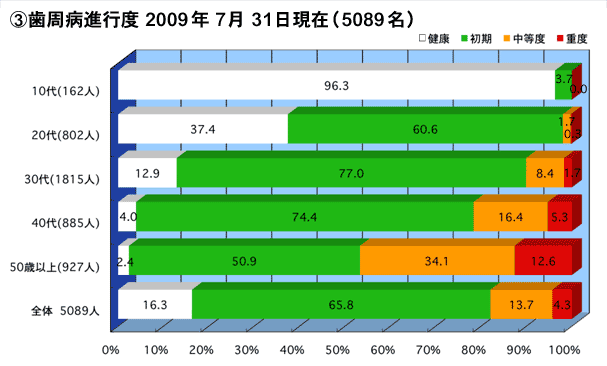 | |||
| (3) 歯周病は、歯の回りの骨(歯槽骨)が溶ける病気です。骨の吸収(骨が溶けること)の程度によって、進行度を分類します。 | |||
| 健 康=現時点で、歯周病の進行は見られない方です。しかし、年齢が若いと健康である確率は高いですから、安心とは言えません。日頃の意識が重要です。 初 期=平均の骨吸収量が30%未満の方ですが、吸収がある程度判断できる方です。歯周病は30歳から始まる病気でもあり、早期にその原因を取り除くことで、将来、進行することをある程度予防することは可能です。体質的に免疫力がない場合でなければ、早期の介入がとても有効です。骨の吸収がなくても、歯肉が炎症を起こして、腫れている場合もあります。こういった方は、歯周病予備軍です。10代でも見られます。 中等度=平均の骨吸収量が30%から50%の方で、十分な治療管理を行わないと重度になっていきます。 重 度=平均の骨吸収量が50%以上の方で、残せない歯も多くなります この結果では、30代になると、10%の方に歯周病の重傷者が見られます。さらに、50代以上では実に50の方が、重傷な歯周病で苦しんでいます。全体としては、重傷な方は、来院者の20%ですが、これらの方々は、歯周病の積極的な治療、メインテナンスが必要です。また、残りの方も、管理は要らないということではなく、初期程度のうちに管理しておけば、将来の進行を予防できると思います。
| |||
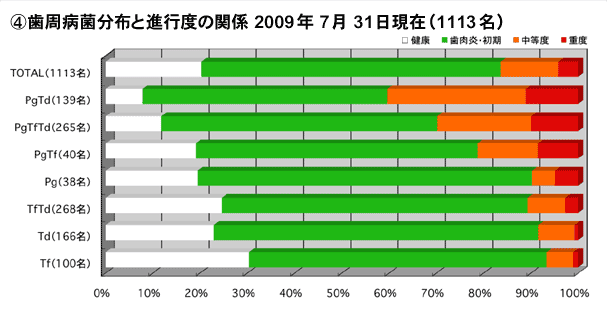 | |||
| (4)これは、当医院で行っている歯周病原菌の遺伝子検査の結果判明した菌種と歯周病進行度の相関を示したものです。この中で、Pg、Tf、Tdという3種の細菌の保菌状態と現在の歯周病の進行度をグラフ化したものです。縦軸の項目は感染状態を示し、複数の感染の場合は最近の名称を列挙してあります(例:PgとTdの複合感染はPgTdとなります)。これを見ると、全体では、中等度以上のハイリスク患者は20%になることがわかりますが、特に、PgTd混合感染、PgTfTd混合感染、PgTf混合感染の場合、有意にハイリスク者が多いことがわかります。このことから、主に、Pg菌を保菌しているかどうかが歯周病の悪化度に関係しているようです。現在、歯周病が悪い人は、当然Pg菌の保菌が多いのですが、現在、明らかに歯周病に罹患していない人でも、Pg菌を保菌している場合は、将来歯周病のリスクは高くなることが予想されるので、今のうちから予防管理をした方がいいということがわかります。ご自分の菌感染状況を調べると、将来の予測ができるということが分かってきています。 この結果は、当医院オリジナルであり、現在、アメリカ歯周病学会に報告するべく東京医科歯科大学歯周病学教室のご協力のもと論文化に向けて作業中です。
| |||
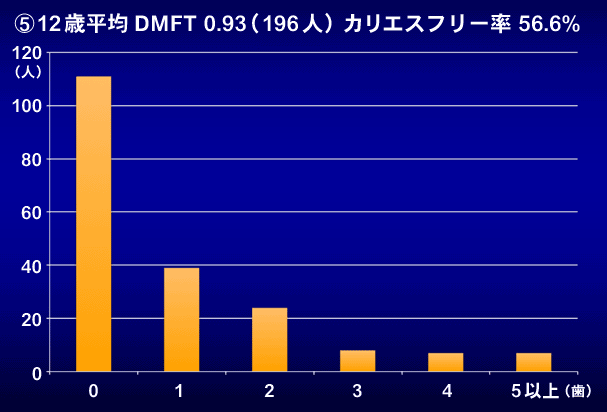 | |||
(5)グラフは当医院に来院した児童の12歳時の虫歯本数(治療中、治療済を含む)と人数の分布。縦軸は人数、横軸は虫歯の本数。DMFT(未処置の虫歯、虫歯が原因で抜かれた歯、虫歯を治療した歯の合計を人数で割った数)の平均値と全く虫歯になったことが無い虫歯ゼロ率(カリエスフリー率)です。平均DMFTは0.93、カリエスフリー率は56.6%でした。平成17年度歯科疾患実態調査(7年ごとにデータ収集)では、DMFTは1.7、カリエスフリー率は40%でしたから、当医院に来院することで、DMFT、カリエスフリー率ともに、一般平均より改善されています。
| |||
 | |||
(6)これは、当医院に来院した患者の20歳時での平均虫歯本数DMFTと虫歯ゼロ率です。DMFT平均8.35、カリエスフリー率4.7%で、これは、歯科疾患実態調査と大差ありません。これは、この年齢層の患者さんは、非常に来院が途絶えがちで、何か問題が発生しないと来院しないからです。従って、当医院で十分にメインテナンスを受けている方が少ないので、データは、一般平均と同じになるのです。今後は、こういった患者層への働きかけが重要だと認識しています。
| |||
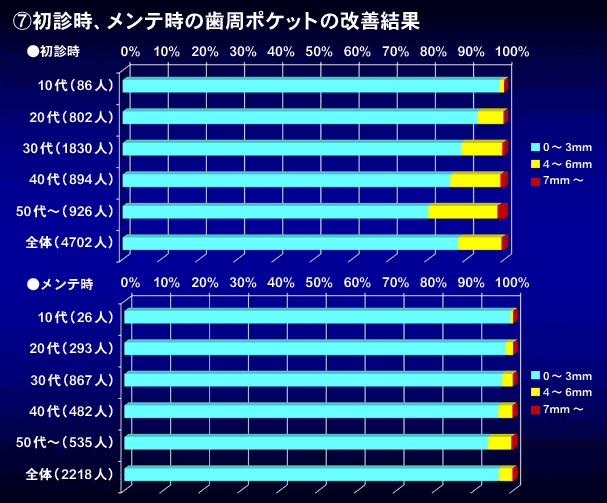 | |||
| (7)歯周病は、歯の回りの歯周ポケットの測定を通じて、状況を把握します。 このグラフでは、現在歯周病治療を終えてメインテナンスを受けている方2218名の初診時と現在のポケットの測定結果です。これを見ると、初診時に20%近い人に見られていた、深い歯周ポケットがかなり減少していることがわかります。 完全に治っていない方も見られますが、多くの方では、治療により、その後継続したメインテナンスを受けることで歯周病の進行が抑制されていることがわかります。
| |||
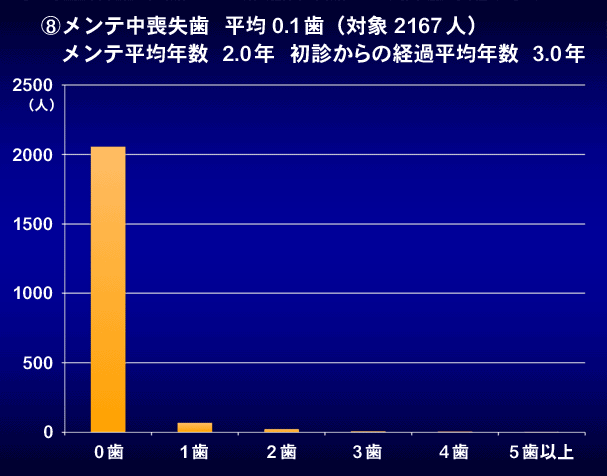 | |||
| (8)最後は、一番蓄積するのが困難なデータです。メインテナンスに来院している患者さんが、自分の歯を失わずに過ごせているかを調べているものです。開設以来、対象者は2167名、初診からの経過年数の平均は3.0年、メインテナンス平均経過年数は2.0年です。その方々のこの期間中の平均喪失歯(虫歯や歯周病で失った歯)の数は、0.1本でした。年齢別のデータ集計や、歯科疾患実態調査との差の比較等は今後の課題ですが、データを長く取っていると、さらにこの歯科医院を利用することによる利益が浮き彫りになるはずです。 |
■このページのトップへ戻る■
| ■2009年8月20日 8月4日 第9回スタッフミーティングを開催いたしました |
 去る8月4日(火曜日)午後、当医院セミナー室にて、当医院恒例のスタッフミーティングを開催しました。2005年にスタートした半年に一回のこのイベントは、今回で9回目になりました。このミーティングの目的は、半年間を振り返り、自己目標の達成評価、医院における自分の役割評価を通じて、次半期に向けて、全員の前で決意表明するイベントです。一人あたり15分程度の時間で、スライドプレゼンを行い、質疑応答を行います。半年ごとに行われることで、お互いに刺激を受け、また自己啓発も行われ、その結果、自分の仕事への意欲の向上、ひいては、患者さんへの対応の満足度を上げる行動に繋がると考えております。当医院では、単に、患者さんの治療を行うことだけが歯科医院の使命だとは考えておりません。来院される患者さんが、来て良かったと思える満足度が得られることを目標にしております。その点で、こういったイベントを通じて、全員のモチベーションが向上されることは好ましいことだと思っております。今後も定期的に続けて参ります。 去る8月4日(火曜日)午後、当医院セミナー室にて、当医院恒例のスタッフミーティングを開催しました。2005年にスタートした半年に一回のこのイベントは、今回で9回目になりました。このミーティングの目的は、半年間を振り返り、自己目標の達成評価、医院における自分の役割評価を通じて、次半期に向けて、全員の前で決意表明するイベントです。一人あたり15分程度の時間で、スライドプレゼンを行い、質疑応答を行います。半年ごとに行われることで、お互いに刺激を受け、また自己啓発も行われ、その結果、自分の仕事への意欲の向上、ひいては、患者さんへの対応の満足度を上げる行動に繋がると考えております。当医院では、単に、患者さんの治療を行うことだけが歯科医院の使命だとは考えておりません。来院される患者さんが、来て良かったと思える満足度が得られることを目標にしております。その点で、こういったイベントを通じて、全員のモチベーションが向上されることは好ましいことだと思っております。今後も定期的に続けて参ります。今回は、ミーティング終了時のスタッフの感想報告を掲載します。 患者さんひとりひとりに満足していただけるよう頑張ります! 助手A(勤務3年、経験10年) 暑い中、お疲れ様でした。 前回のミーティングより、皆さん、とてもカラフルなプレゼンで驚きました。内容も細かく調べ、グラフや絵にしたり、写真が入ってたり、個性あふれるプレゼンでした。私も3回目になるので何となくですが、プレゼンの流れみたいなことが分かってきたように思います。 今、来院している患者さんひとりひとりが満足して帰っていただけるよう毎日思いやりをもって頑張ります! スタッフミーティングを行うといつも身が引き締まる思いがします 助手B(勤務3年、経験5年) スタッフミーティングを行うといつも身が引き締まる思いがします。ただ漠然と働いている訳ではなく、スタッフがそれぞれが医院の事を考えたり、自分自身のスキルアップを考えていたり、患者満足度を考えて進んでいるのだなということに感心しました。また、半年間、目標に向かって頑張っていきたいと思います。 日々の積み重ねをわすれぬよう努力したいと思います 歯科衛生士A(勤務7年目、経験20年) それぞれの職域で、患者さんを考え、いろいろと工夫している感じがよくわかりました。 そして、スタッフミーティングに向けての資料作りもそれぞれ頑張っている感じが伝わり、よい刺激になります。 今後も自分の立場では何が要求されるのかを日々考え、患者さんのためになる対応を心がけ、いろいろな面での日々の積み重ねをわすれぬよう努力したいと思います。 また、半年後充実した発表ができるようコツコツ頑張りたいと思います。 自分の甘かったところを意識していきたいと思います 歯科衛生士B(勤務6年目、経験5年) 見えないところでみんな頑張っているんだなと感じました。自分の甘かったところを意識していきたいと思います。作業が遅いので、皆に迷惑にならないように機敏に動くよう努めたいと思います。チームワークを意識し、協力し合って効率よく仕事がでるようにしていきたいです。 治療サイドでは、どう動けば患者さんの待ち時間が少なくできるかを考えます。 予防サイドでは、患者さんにご自分のリスクを理解してもらって、それを念頭において、メインテナンスや初期治療に来院してもらえるようにモチベーション頑張ります。 中山先生のセミナーで、スキルアップができるように勉強することを楽しみにしています。 目標を持って、クリニックとともに向上していこうとする姿勢が伝わってきました 歯科医師(後期から研修医予定、経験0年) プレゼンを聴き、スタッフ一人一人が目標を持って、クリニックとともに向上していこうとする姿勢が伝わってきました。大学病院だとチーム医療といいながら、ドクター同士はバラバラで衛生士などとのスタッフとの連携が希薄なように思いました。また、清潔面やコストに関する意識も大学では低いように思います。このクリニックでは、一つ一つの問題を全員の力で解決し、さらに良くしていこうという考えがあり、10月からの研修生活がとても有意義なものになると期待できました。 10月からの研修、よろしくお願いします。 |
■このページのトップへ戻る■
| ■2009年7月2日 つくば市マタニティー講演会でお話しております |
 昨年度から、歯科医師会の関係で、つくば市保健センターが開催するつくば市マタニティー講演会で講師を勤めさせていただいております。この6月13日にお話して参りました。 昨年度から、歯科医師会の関係で、つくば市保健センターが開催するつくば市マタニティー講演会で講師を勤めさせていただいております。この6月13日にお話して参りました。年間4回の講演がありまして、“生まれてくるお子さんの歯の知識と、虫歯予防、母子感染について”約1時間講話させていただいています。毎回、お聞きになる方は異なりますので、話しは同じです。皆さん、熱心に聞かれていらっしゃって、ご夫婦連れの方も目につきます。これから、生まれてくるお子さんに、期待と同時に、様々な不安もあろうかと思いますが、歯医者として、正しい知識を持っていただくことは、とても大切な使命と考えて、お引き受けしております。 昨年は、つくば市カピオで開催されましたが、今年は、研究学園都市駅前のショッピングモール・イーアスつくばのホールにて開催しています。買い物のついでにも聞けるので、参加の方も増えてるようです。 |
 ご参加された方が、その後、歯科医院を受診されるケースもあり、皆さんの関心の高さに驚かされます。歯科の情報は意外と正しく伝えられていないことが多いので、機会あれば、今後もこのような院外の活動も、歯科医師会と協力しながら続けていきたいと思います。 ご参加された方が、その後、歯科医院を受診されるケースもあり、皆さんの関心の高さに驚かされます。歯科の情報は意外と正しく伝えられていないことが多いので、機会あれば、今後もこのような院外の活動も、歯科医師会と協力しながら続けていきたいと思います。本年度は、6月、9月、12月、そして、来年3月に予定されていますので、詳しくは、つくば市広報までお問い合わせください。 |
■このページのトップへ戻る■
| ■2009年3月 7周年を迎えました | |
 |
つくばヘルスケア歯科クリニックは2003年の開設以来、丸6年を経過し、7年目に入りました。 約10,000人に近い方が来院され、約3,000人の方が定期的メンテナンスで来院を継続されています。 ホームページでは、ごあいさつのページを更新。これからの「つくばヘルスケア歯科クリニック」のあり方についてご紹介しております。 ぜひ、ご一読ください。 >>詳しく・ごあいさつ・院長略歴 |
■このページのトップへ戻る■
| ■2009年2月5日 ISO9001認証更新審査を受け、ISO9001:2008 認証を受けました | |
 |
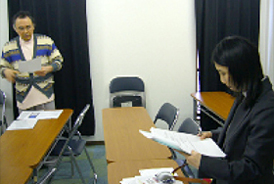 |
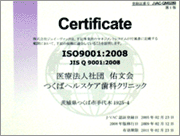 去る2月5日木曜日、当医院のISO9001審査が審査機関「J-VAC」の高久審査員によって行われました。朝8時30分に開始され、9時から院長が経営者インタビュー、10時30分からは、ISO委員長三輪、品質管理責任者飯島が審査を受けました。ISO認証は、1年ごとに更新され、今年は5回目を迎えました。新しい認証基準「ISO9001:2008」に適合していることが確認されました。 去る2月5日木曜日、当医院のISO9001審査が審査機関「J-VAC」の高久審査員によって行われました。朝8時30分に開始され、9時から院長が経営者インタビュー、10時30分からは、ISO委員長三輪、品質管理責任者飯島が審査を受けました。ISO認証は、1年ごとに更新され、今年は5回目を迎えました。新しい認証基準「ISO9001:2008」に適合していることが確認されました。医療の質が問われて久しい現在の医療情勢ですが、このような第三者のチェックを受けるということが、事故防止、満足度の向上という観点から評価されるようになると確信しております。 院長 |
|
■このページのトップへ戻る■
| ■2009年1月23日 2008年版、患者満足度調査を掲載しました |
 去る2008年12月1日~13日にご協力をお願いいたしました、患者満足度調査の結果を掲載しました。 去る2008年12月1日~13日にご協力をお願いいたしました、患者満足度調査の結果を掲載しました。つくばヘルスケア歯科クリニックでは定期的に患者さんからのご意見を伺い、より快適で適確な治療と予防を行う歯科医院創りに役立てています。 ご意見について院長からのコメントも掲載しております。是非ご覧ください。 今回も貴重なご意見、ありがとうございました。 詳しく:患者満足度調査> |
■このページのトップへ戻る■
| ■2009年1月22日 2008年10月29日開催の中山セミナーのご報告 | |
 |
去る2008年10月29日、つくばヘルスケア歯科クリニック内セミナールームにて、シアトル開業の歯周病専門医 中山 吉成先生をお迎えして、同年2月に続いて2回目となる「中山セミナー」を開催いたしました。 今回は特に、相互実習に力を入れていただき、中山先生の持つ技術をの実際に身をもって体験し、指導を得ることでスタッフ全員が高いレベルの技術を学ぶ機会となりました。 >>くわしく:第2回 中山セミナー(ニュースアーカイブ) |